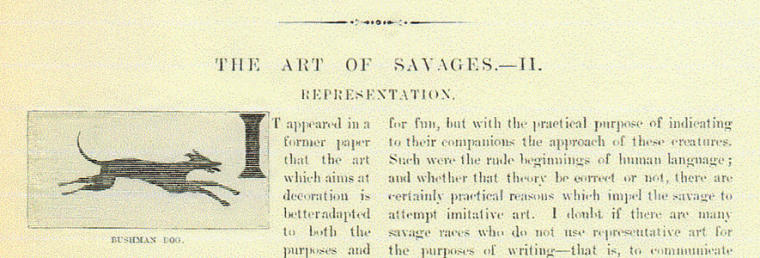当時のイギリスと未開人の芸術の表現方法の類似点を強調している個所に注目したいと思います。人骨の調査をする形質人類学の専門家がヨーロッパと未開人の違いを強調することによって、ヨーロッパ人の優位性を浮かび上がらせることを目的としていたのに対し、ラングは類似性に着目することによって、アーリア人優位の時代に異を唱えたと読めるからです。
The Magazine of Art (1882)掲載のラングの「未開人の芸術」の第一部「I—装飾美術」は4月号に掲載され、第二部「II—描写」(The Art of Savages.—II. Representation.(注1))は5月号に掲載されました。今回は、当時のイギリスと未開人の芸術の表現方法の類似点を強調している個所に注目したいと思います。「ラングの未開人論(3)」で紹介したように、人骨の調査をする形質人類学の専門家がヨーロッパと未開人の違いを強調することによって、ヨーロッパ人の優位性を浮かび上がらせることを目的としていたのに対し、ラングは類似性に着目することによって、アーリア人優位の時代に異を唱えたと読めるからです。
この記事は文章の最初の字をドロップ・キャップ(Drop Cap)という飾り文字を使っていますが、この手法に、アフリカの「ブッシュマンの犬」の絵の1部なのか、先住民族のアートに似せた飾り文字に使っています。最初の文章は”It appeared in a former paper that the art which aims at decoration is better adapted to both the purposes and materials of savages than the art which aims at representation”(前の記事では、装飾を目的とする芸術は描写を目的とする芸術よりも、未開人の目的と材料に適していると述べた)で、最初の文字”I”をドロップ・キャップにしています。走る犬の絵と文の内容とが重なり、巧みなデザインで、これはラングのアイディアなのか、編者のヘンリーか、デザイン担当者がいたのかはわかりませんが、他にも日本の団扇をドロップ・キャップに使うなど、魅力的な装飾が施されていますので、後にご紹介します。
未開人の芸術 II 描写(pp.303〜307)
この記事では「国会の審議中に雄鶏の鳴き声を真似る議員」が「そのスキルを行使するのに私心のない喜びを感じている」のに対し、「未開人」が動物の真似をする時は論理的合理的な理由があると、19世紀の「文明人」の愚かさを皮肉に辛辣に述べています。21世紀の日本では首相が国会審議中に何度も「ヤジ」を飛ばしていることが話題になっています(注2)。以下が「未開人の芸術II」の主要部分です。
今回は未開人がいかに努力して表現しようとしたかを見なければならない。ここでも、未開人がどんな目的に触発され、どんな材料が手に入るのかを検討しなければならない。未開人の絵には実際的な目的があり、模倣のための模倣が好きだからなどと簡単に結論付けてはならない。確かに、現代のモダン・アートは絵画や彫刻で自然を模倣したいという気持ちが生来の衝動、もって生まれた本能になっているかもしれない。しかし、そうなる理由があったに違いない。私たちが模倣芸術に対する私心のない愛をはるか昔の祖先から受け継いでいる可能性もないわけではないが、彼らの模倣癖には直接的で、私心のある、実際的な目的があった。国会の審議中に雄鶏の鳴き声を真似る議員や、暇つぶしに犬のように吠える浮浪少年(street boy)などは、そのスキルを行使するのに私心のない喜びを感じている。
しかし進歩的な知識人は同意すると思うが、犬や雄鶏やその他の動物の声を真似た最初の人びとは、単に楽しくてやったわけではない。仲間にこれらの動物が近づいていると知らせるという実際的な目的があったのだ。(中略)この理論が正しいか否かは別として、未開人が模倣芸術を試さなければならない実際的理由は確かにあったのだ。(中略)
ここに掲載しているアメリカ・インディアン(Red Indian)の絵文字(picture-writing)は北米の原住民に関するコール[Johann Georg Kohl: 1808〜1878,ドイツの地理学者]の本(注3)から採ったものだ。読者はこの未熟な芸術品をたいして重要ではないと思うかもしれないが、実は大洪水を記録したカルデアの粘土板と同じくらい重要な文書なのである。荒っぽく描かれた人物たちはこのアーティストの心にはManabozhoの神話を呼び起こすもので、それはこの大きな湖のそばに住む人びとにとっては、プロメテウスとデウカリオン(注4)、あるいはカインとノアに匹敵する。Manabozhoは偉大な酋長で、二人の妻がいたが、二人は喧嘩していた。ずんぐりした2人の姿[コールの絵で4番が付されている両脇の人物]がこの妻たちを示している。2人の間にある塚はManabozhoの不快感を表している。その隣に見えるのは2本の木にはさまれたManabozhoで、困った状況だが、狼もリスもManabozhoを救うのを拒否している。ピラミッドのような山の上に人がいる図は、Manabozhoが祖母を洪水から守るために置いたことを示している。同じような図が[隣の]自分の山の上にいるManabozhoである。次に見える動物たちは、洪水がどの程度かを確認するためにManabozhoが送り、同時に祖母にメッセージを伝えるために送られた動物たちである。この巻物は文学的素養のあるアメリカインディアンによって、多分白樺の皮に描かれ、コールに差し出された(その動作が右下に描かれている)のは、Manabozhoの洪水のストーリーを決して忘れないためである。ヨーロッパ人が知る限り、アメリカインディアンはいつもこの絵文字を、彼らの伝説や詩やまじないを記憶するために使っている。言うまでもなく、メキシコの絵文字も古代エジプトの象形文字も同じ未開のプロセスから生じている。(中略)
図の出典:J.G. コール『スペリオル湖周辺の旅』(1860)、J.G. Kohl, Kitchi-Gami. Wanderings round Lake Superior, Chapman and Hall, London, 1860, p.387.
図の題名:「もう1つの白樺の皮」(Another Birch Bark)
絵文字に加えて、宗教も未開人の具象芸術を発展させた。トカゲかクマを崇拝する人はトカゲやクマを表したお守りや偶像を身につけるのが便利だと思うだろう。未開人の世界観は、似たものは似たものに影響を与えるという理論である。これが肖像画に描かれている人を燃やす行為の源である。ケープ[Cape:南アフリカ]の入植者たちがグラッドストーン氏[William Ewart Gladstone: 1809〜1898, この当時のイギリス首相]の肖像を燃やした時、この政治家に危害を加えてはいないとよくわかっていた。しかし、この儀式を未開時代から引き継いでいて、人間の肖像を燃やしたり、槍で突き刺したり、肖像が蝋人形なら火で溶かしたりすることは、生きている人を溶かし、消し去ることと考えられていた。この考え方は、人間とその肖像を共通とみなす理由からきている。この考え方は未開人が肖像画を描かせないことにつながる。彼らは、肖像画が魔法や悪意のある使い方にされると考えたのだろう。しかし、もしトカゲやクマを崇拝しているなら、祈りや崇拝の行為を動物の像に向かってするなら、その動物たち自身が喜び、動物たちに幸運をもたらすとも考えただろう。
コールの本から図を採用して、図の意味を説明しているラングの注目点に対し、コールがこの絵を描いたインディアンから実際に聞いた説明がどうだったか、要約します。
No.1:地上を流れる川
No.2:華やかな戦闘装束のMenaboju(Manabozhoの変化形)。彼は偉大な勇士の酋長。
No.3: Menabojuの家。ここで2人の妻と暮らした。
No.4: 2人の妻が大げんかをし、間にある岩はMenabojuの「止めろ」という命令を表す。
No.5: 森でよく起こることは、隣あった木の枝が風でこすれ、森中にこすりあう音が響いたり、こすれる熱で火事が起こったりする。Menabojuはその音を止めようとしたか、山火事を恐れてか、枝を折ろうと木に登り、挟まってしまう。そこに3日間はさまったまま、飲まず食わずで、通りかかる動物たちに助けを求めるが、最初に来た狼は「あれ、Menabojuよ! お前さん、そこでちゃんと守られてるよ!」と言って、木の下で朝ごはんを食べ、残りを布にくるんで木の下に置いて行ってしまった。次に来たリスはMenabojuに懇願されて、木をかじり始めたが、歯が痛くなったと言った。彼らは甘いナッツを砕くのには慣れているが、こんな硬い木を切る仕事には慣れていないと言い、他の動物たちも同じような弁解をしたが、そのうち、クマが来てMenabojuを苦境から救ってくれた。
No.6: Menabojuの孫が狩りに出て、川に行くと、カメの王がいたので、向こう岸に連れて行ってくれと頼む。カメの王は悪者で、助ける代わりに川を広げてしまい、孫は渡ろうとして溺れてしまう。カメは孫を食べてしまうが、その最中にMenabojuに殺される。カメたちはMenabojuに宣戦布告して、大洪水を起こす。
No.7: Menabojuは最初に祖母を高い山の上に連れて行く。彼自身も世界一高い山の一番高い松の木に登り、洪水が引くのを待つ。彼の両側に描いた鳥のアビとマスクラットは彼のもとに来た動物だ。
No.9: 2つの島はMenabojuが作ったもので、小さい方は彼の重さに耐えられない、大きいものは彼を支えられ、これが新世界になった。
No.10: Menabojuは祖母を探し、世界が新たに創造されたことを知らせて、祖母に戻ってくるように伝えるため、動物たちを送った。Menabojuが世界を戻した後、すべての鳥、動物、人間を呼んで、自分に出陣化粧を施し、頭に強さの象徴のツノをつけ、手には槍を持ち、演説をした。「野蛮人であるわれわれの子どもたちは絶えず戦をするだろう。時には和平に調印するだろう。したがって、平和と戦争の法律が制定されなければならない」と。
首相の肖像を燃やす抗議行動
ラングのグラッドストーン首相に関する言及について、1880年代初頭のイギリスの植民地政策を知らないと、なぜ南アフリカの入植者たちが首相の肖像を燃やしたのかわかりませんし、ラングのスタンスがどのようなものだったかも理解できません。この背景を解説した論文「ユニオンジャックを葬る−−第一次ボーア戦争(1880〜1881)中のトランスヴァールのイギリス忠誠者たち−−」(注5)から抄訳しますが、1870年代以前の南アフリカについて以下に概略します。
- 1795年:イギリスがフランスに対抗して、ケープを占領する。
- 1815年:ケープはオランダ領に戻る期間を経て、再びイギリスが領有権を得た。
- 1843年:イギリスがナタール(Natal)を併合。
- 1852年:ボーア人(オランダ系移民の子孫)による南アフリカ共和国(トランスヴァール共和国)設立。
- 1854年:ボーア人のオレンジ自由国が設立された。
- 1871年:1860年代後半にヴァール川とキンバリーでダイアモンド鉱山が見つかり、イギリスがダイアモンド鉱山を併合。
- 1877年:イギリスがトランスヴァールを併合。ボーア人の抵抗が激しくなる。
1877年〜1881年のトランスヴァールには、オランダ系が36,000人、非オランダ系ヨーロッパ人が5,000人、その大多数がイギリス系だった。アフリカ人は70万〜80万人で、全人口のわずか5%が白人で、そのうち非オランダ系が14%以下という人口構成だった。
しかし、このわずかなイギリス系入植者は数に反比例した影響力を持ち、町でも鉱山でも田舎でも、商業があるところにはイギリス人が優勢だった。行政面でのイギリスの影響力も次第に大きくなり、官僚を国籍別に見ると、オランダ系アフリカンダー(Dutch Afrikanders,ケープ生まれのオランダ系)80人に対し、イギリス系アフリカンダー41人、イギリス人68人、オランダ人35人、ドイツ人28人その他だった。1880年に立法議会が始まったが、オランダ語と英語で行わなければならず、そのメンバーの間の大きな違いが浮き彫りになった。
このような不安定な状況の中で、少数派のイギリス系が新植民地の中でアイデンティティを保てるのはイギリス的(Britishness)であることを主張し、王室と国旗への誇張した忠誠心にしがみつくことによって、将来の安定と繁栄をイギリス統治の維持に頼ることだった。この地を訪れた小説家のアンソニー・トロロープ[Anthony Trollope: 1815〜1882]は「地球上のどこにいても、イギリス人は周囲の誰よりも自分が優れていると思っている」と言ったが、この感じ方は特に[トランスヴァールの]都市部に住んでいるイギリス人に強く、イギリス軍に守られていると信じているため、イギリス統治に対するボーア人の高まる不満を嘲り、ボーア人を田舎者と見下していた。
グラッドストーンが1880年4月にリベラル政権を立ち上げた。トーリー党[保守党]の同盟政策も、トランスヴァールの併合も支持しないグラッドストーンだったが、1880年6月にイギリス統治を廃止しないと再確認した。この明確な再確認はトランスヴァールに多くのイギリス人が移住することを後押しし、すでに入植している人々がこの国にさらなる投資をすることを促した。
1880年12月にボーア人による反乱が起こり、イギリス軍との戦闘で、1881年2月にイギリス軍が敗北して、3月にボーア人と休戦を締結した。長い交渉の末、1881年8月に協定が締結されて、権力の移譲を示す共和国の旗が掲げられた。グラッドストーンが求めたのは南アフリカのオランダ人を安心させ、南アフリカ全体でのアフリカーナ[オランダ系白人]の反乱を防ぐことだった。イギリス政府はイギリス忠誠者がこの国に住み続け、あらゆる公民権を享受し、財産の保護を約束したが、トランスヴァールのイギリス人はグラッドストーンが裏切ったと受け取って、政府に対する誓願書がイギリスに送られた。帝国政府が何度もトランスヴァールはイギリス領のままだと約束したので、この土地に莫大な投資をしたが、それが危うくなっていると言った。「銀行も資本家も逃げ、あらゆる企業が麻痺状態である。不動産は売れず、極端に値下がりしている。残酷にも母国に騙された。失った資産の全額の補償を要求する」という誓願書だった。このような誓願書や供述書が次々と送られ、グラッドストーンに対する怒りが高まっていった。
3月から4月にかけて、トランスヴァールの各地でグラッドストーンの肖像が燃やされる抗議活動が起こった。ある町では礼服を着たグラッドストーンの人形の首に縄が巻かれ、葬儀用の車に乗せられ、「リベラル内閣」と書かれた棺桶と共に、町を練り歩かされた挙句、町の広場で絞首刑にされて燃やされた。人形として6回も燃やされたにもかかわらず、グラッドストーンは信念を曲げなかった。彼は自分が適切だと思う回答をトランスヴァールのイギリス人たちに返した。停戦と南アフリカの同盟政策の破棄とトランスヴァールの返還を巧みに正当化した後、忠誠者たちの協力に感謝して、資産と公民権を保証すると約束したが、「政策の変更による資産の減価償却に関する補償要求は認められない」と書いている。
トランスヴァールのイギリス人は1880〜1881年のトランスヴァール戦争で比較的無傷だった。住み続けた者たちは民族浄化にもあわなかったし、迫害という被害にもあわなかった。彼らの物質的損失はボーア政府が補償の支払いをしない場合、イギリス政府が支払った。商売上の損失は彼らが言うほど大きくなかった。間接的な損失に関しては、トランスヴァールに残ったイギリス人、あるいは投資を続けたイギリス人は1886年の金鉱の発見によって10倍になって報われた。
イギリス人入植者たちが首相の肖像や人形を燃やす行為を、ラングが未開人の儀式と比較したことは、1877年の彼のコメントにつながっているように思います。この当時のイギリス人、特に植民地の入植者たちが人種的優越を感じていたことを、メンタリティーにおいて未開人と文明人と変わりないと示したと読めるのではないでしょうか。この後に続くラングの解説にも、未開人と文明人の共通点、特に南アフリカの先住民族の芸術から見えることを説いています。
上記の論文(2004)の疑問点は、1877〜1881年に70万〜80万人もいたという先住民族の運命について何も触れていないことです。まるで存在しないかのような21世紀の視点に比べ、1882年のラングの視点は先住民族の芸術から学べることがいかに大きいかというものです。
現在の南アフリカ政府ホームページに記載されている歴史によると、先住民族は「白人の南アフリカ」には属しておらず、「部族社会」に属しているアフリカ人は「白人のニーズ」のために働かされていたこと、南アフリカの地方自治体はアフリカ人を別の場所に閉じ込めたこと、この政策が1948年から始まるアパルトヘイト(隔離政策)に発展していったといいます(注6)。
注
| 注1 | The art of savages—II Representation”, The Magazine of Art, Vol.5, 1882, Cassell Petters Galpin & Co., pp.303-307. https://archive.org/details/magazineofart05londuoft |
|---|---|
| 注2 | 石松恒「安倍首相、またヤジ 誤答弁の指摘に『いいじゃないか』」『朝日新聞DIGITAL』2015年8月31日 http://digital.asahi.com/articles/ASH8P5SG3H8PUTFK00X.html |
| 注3 | コールのどの本か、ラングは出典を示していませんが、インターネット・アーカイブ所蔵のコールの著作75点を調べた結果、次の本からの引用とわかりましたので、コールの本に掲載されている図を採用します。ラングの記事には番号は付していませんが、同一のものです。 J.G. Kohl, Kitchi-Gami. Wanderings round Lake Superior, Chapman and Hall, London, 1860. https://archive.org/details/kitchigamiwande00wraxgoog |
| 注4 | プロメテウスとデウカリオンについては、ギリシャ哲学の専門家、小澤克彦氏のサイトの解説がわかりやすいので、参照してください。「5.プロメテウスの神話」 http://www.ozawa-katsuhiko.com/3greece_syudai/greece_syudai_text/greece_syudai05.html |
| 注5 | John Laband, “Burying the Union Jack: British Loyalists in the Transvaal During the First Anglo-Boer War, 1880-1881”, History of Intellectual Culture, Vol.4, No.1, 2004. http://www.ucalgary.ca/hic/issues/vol4/4 |
| 注6 | ”History”, South African Government, p.8. http://www.gov.za/about-sa/history |